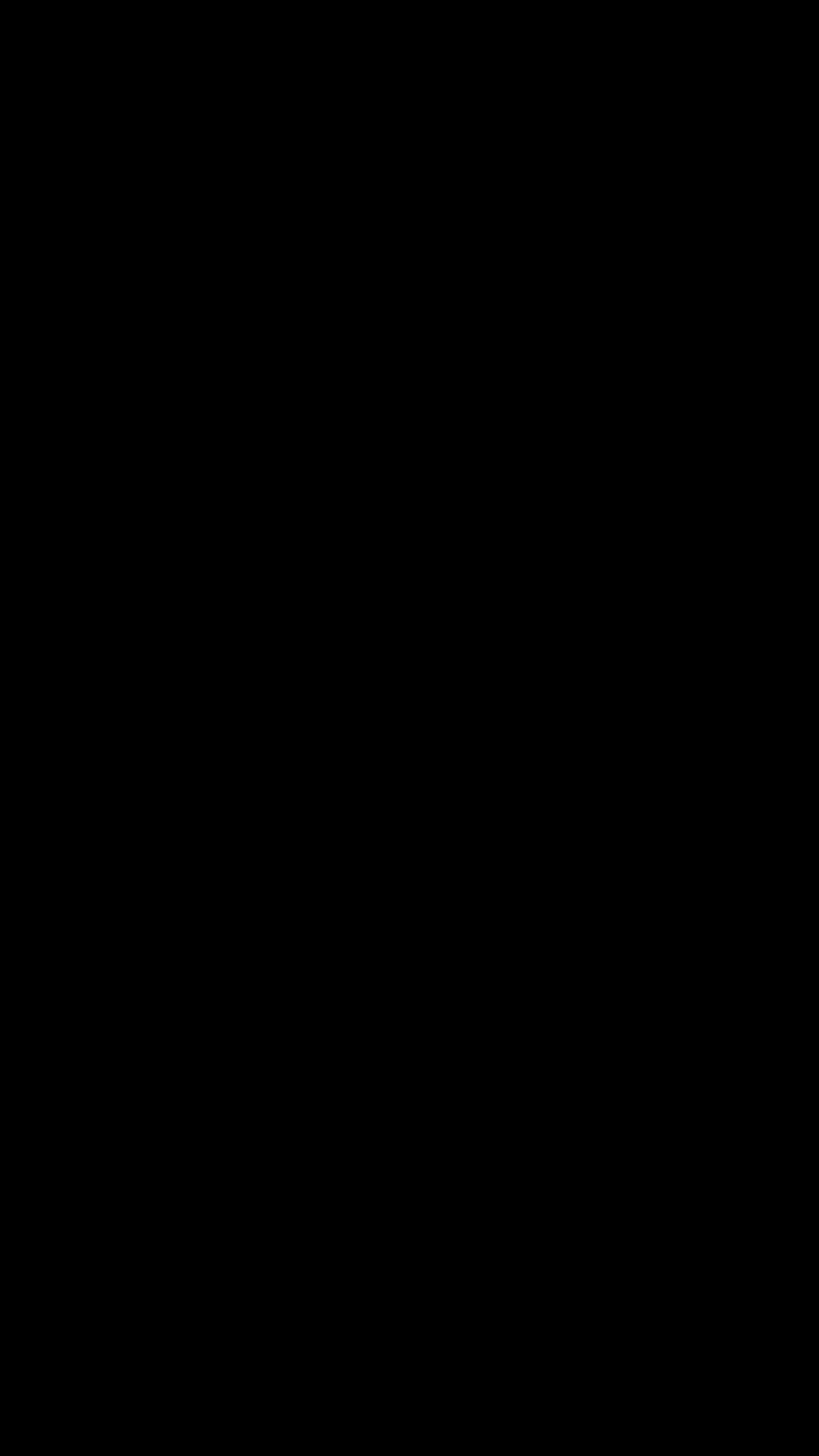それぞれの
2022/03/03
今日はひなまつり。集会行事は学年で分散しているので、私のみ3回出席して、それぞれの学年で担任の先生方が司会をします。つまり私だけが3通りの司会を見られるわけで、なかなか興味深かったです。

まず年中組さん。「お人形はね、昔は病気や怪我を移して(身代わりに)なってもらったんですって。流し雛って言うのよ。今は「みんな元気で大きくなって」という嬉しい姿だけれど、そういう切実な願いを引き受けたものだったのよ」という趣旨の話をしていました。歴史的に「人形(ひとがた)」にはそういった役割がありました。「それを踏まえてこその育ってきたことの嬉しさ・有り難さ」が行事の大切なところで、表面的な「お祝い」ではないことを、しっかり示していました。
次いで年少さんでは、先生がスケッチブックに絵を描いて説明してくれました。「幼稚園に飾ってあるお雛様。みんなよく見たことあるかな?」ということで、それぞれを紹介しつつ「じっくり見ること」に期待を持たせていました。「あの様子は、結婚式なんだよ」ということも伝えてくれ、(時代は違いますが)ご両親の結婚式(ないし披露宴)をイメージした子もいたかも知れません。「具体的に見る」ことは子どもの得意なこと。それを促してくれました。
最後は年長さん。私も「全部で何人いるか知ってる?」とクイズ調で話を進めました。ひとがたの話も「人形は、病気や怪我を治して欲しくて使ったんだって。どうやったと思う?」という質問形式に。それを受けて司会の先生も「子どもたちに聞いてみる」スタイルで進行していました。「女の人のなかで、眉毛のない人がいるんだけれど、どうしてでしょうか?」子どもたちも思わず手をあげます。自分の意見を言う…「昔は鏡がなかったから、見えなかった!」なるほど!…ですが先生は「ちがいます」とあっさり答えました。
そこで、子ども達はどうするかなと思ったのですが、全くめげない。「じゃ、こうかな?」「ああかな?」と、次々に持論を展開しました。とうとう誰にも正解は分からず、先生が答えを明かしました。
この「めげなさ」は、この先生が育てたものだなぁと感じました。本気で考え、思い切って手を挙げ、けれど間違えた。その時にめげない。これは大切な大切な資質だと思います。非認知ではあるけれど力です。
私は園長として、先生方にはそれぞれの個性、それから子どもとの呼吸を大切にして欲しいと思っています。「あの子たちだったら、どう伝えれば興味を持つかな?」と予定していたこと、その場で急に展開すること。どのみち「令和3年度のひなまつり」は一度だけです。どんなやり方をしたって「終わっていくこと」ですから、精一杯で臨まないと勿体ないですよね。
--------------------------------------------------------------------
明照幼稚園
住所:
東京都文京区小石川4-12-8
電話番号① :
03-3815-0166
電話番号② :
03-3811-1306
--------------------------------------------------------------------